唐織とは
唐織は中国(唐)から渡来した織物が融合し生まれた極めて装飾性の高い美術織物を源流とした西陣を代表する絹織物ですが、唐織の「唐」は、中国から請来されたという意味ではなく、優れたものの美称として用いられています。
日本が誇る伝統文化「能」の衣装は、世界でも最も豪華な衣装で表現される演劇です。その中でも、主に女役の演者に用いられる唐織と男役の中の厚板は、時代の粋が込められた浮織で作られています。平安時代の十二単の上着(唐衣)に用いられた浮織組織の技法が進化し、新たな刺繍の趣きと摺り箔美が織箔技術の工夫で加味されて、現代の錦の最も豪華な織物・唐織が完成されました。
経糸は2400本羽二重、横糸は一寸間に90越以上打ち込まれています。尚、それ以下の経糸打ち込みは唐織とは呼びません。
本物の唐織の最大の特徴は、土台になる錦地が生糸の経糸を使った薄い生地で織られ、そのことによって上絵の浮織がレリーフの様に表現されて出来上がることにあります。それにより織上り品が軽くなるのと同時に、しっかりとした張りのある物になり、長時間のご使用が苦痛にならない安心感が生まれるのです。
唐織の表現技法 平面から浮織までのわずかですが、
その段差を利用した唐織は「レリーフの絵画美」が実現できます。
| 唐織の表現技法 Mode of expression |
| 平面から浮織までのわずかですが、 その段差を利用した唐織は「レリーフの絵画美」が実現できます。 |
ここでは織デザインを、唐織によってレリーフ状に表現される技法を説明します。
 |
錦地紋様 土台になる錦地は三綾といわれる経糸2、緯糸1の割合で繰りかえされた織組織です。経糸と緯糸の割合を2:1と1:2の二種類で使用すると経糸と緯糸だけで最も平坦な織絵が表現されます。 |
|---|---|
| 細か伏せ紋様 次に薄い文様は金箔など紙で作られた素材を経糸で押さえて織り込みます。これには箔などの他に、細い金糸、細い糸などで織ることもできます。また箔に模様をつければ、それだけで絵の織物になります。 |
|
| 荒伏せ紋様 浮織と箔織の中間になるものです。経糸をあらかじめ10数本から20数本ごとに使用する糸を決めておき、一定の割合で絵緯糸を押さえる組織です。ここではさらに倍越といって二度縫い取りしたものを紹介します。(金の縫取り) |
|
| 浮織1針とじ紋様 当初の浮織は緯糸を押さえる方法は絵柄の形でしかなかったのですが、大きな柄あるいは長く緯糸が渡ると引っかかりなどで支障をきたしました。桃山時代に職人の技術で所々押さえられていますが、あらかじめ決めて押さえる様になったのは明治にフランスからジャガードが輸入されてからです。今は長くても15mm前後で押さえられています。 |
|
| 浮織2針とじ倍越紋様 浮いた広い面積を浮織1の針とじでは、とじた経糸の太さによって表面に穴の開いた様なくせがでます。(まわりの花の部分) これをなくすために使われる最も手間のかかる、同じ所を二度縫い取る倍越と呼ばれる技法です。(うさぎの部分) |
|
| 生糸について RAWSILK | |
| 昔からの本物の唐織の条件に軽くしっかりと張りのある錦地に、豊かなボリューム感のある浮糸の絵緯で織られたものというのがあります。 薄くて張りのある地は、昔と同じ織り方を再現することにあります。蚕からそのまま生まれた生糸には、セリシンという天然成分と糊状のものが約2~3割ほど絹糸のまわりについています。通常それを練り(ねり)という工程で取り除くのですが、唐織は生糸のままで染色し経糸に使用します。そのことで適度な柔軟性と張りのある薄い錦地が織られ、ボリュームのある浮糸との対比が華麗に演出されます。 尚、天然成分のセリシンのため染色に対して若干の色ムラが生じることがあるのですが、それが純然たる唐織の証明にもなります。 |
|
| よくある唐織Q&A |
| Q1 唐織って何? |
| A 西陣を代表する織物の技法の中の一つです。唐織は古くより武家の重要な儀式や、日本が誇る伝統文化「能」の衣装に使われており、現代の錦の最も豪華な織物といわれております。 |
| Q2 唐織と他の織物の違いは? |
| A 一言で織物と申しましても日本には「紹巴」・「朱珍」・「緞子」・「捩り織」・「ビロード」・「佐賀錦」・「綴れ」・・・・などなどそれぞれ特徴を持った多種多様な織物の技法があります。その織物の中の一つの技法として「唐織」があるのですが、唐織は模様糸を織物表面に浮かせて織りあげるので、立体的な紋様表現(柄)が可能になります。色糸の盛り上がりによる立体感や、色彩豊かで重厚な雰囲気を持っていることが唐織の最大の特徴です。 |
| Q3 唐織の歴史は? |
| A 平安時代の十二単の上着(唐衣)に用いられた浮織組織の技法が進化し、織物・唐織が完成されたといわれております。 |
| Q4 西陣織と唐織は同じ? |
| A 正確にいうと同じではありません。「唐織」は織りの技法の名称であり、「西陣織」というのは地名(京都・西陣)からきた京都西陣の織物の総称です。西陣には唐織以外にも「錦・綴・紹把」などなど、様々な織りの技法があり、唐織を含めそれらすべての総称として「西陣織」と呼ばれます。 |
| Q5 刺繍のようにも見えるが、刺繍と唐織との違いは? |
| A 唐織物は生地を織りながら太い横糸で文様(柄)を織っていくため、浮き上がった文様(柄)が刺繍のように見え、よく刺繍と間違われる方もいらっしゃいますが、刺繍はハンドメイドであり、唐織は機を使って織り上げる、いわゆる「織物」ですので、そもそも組織などがまったく異なるものです。 |
| Q6 主に唐織が用いられるのは? |
| A 唐織は、通常、袋帯・能衣装を中心とし、几帳・打掛・行司衣装などに用いられています。 |

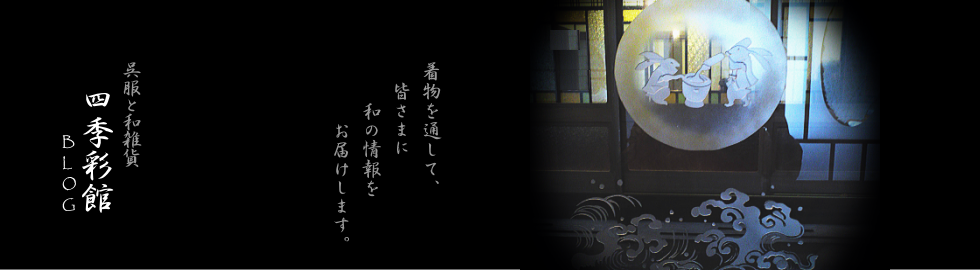
![77443523[1]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/07/7744352311-225x300.jpg)



